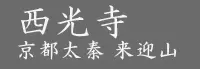西光寺からのお知らせ
2025/10/23 ホームページをリニュアルしました

西光寺について
縁起
京都の洛西にある西光寺は、浄土宗の開祖 法然上人のご遺骸を約8ヶ月間 お隠してお護りした寺院です。 嘉禄3年(1227年)に、法然上人のお念仏の教えに反対した勢力が、大谷 (現知恩院)の法然上人のお墓を破壊して、そのご遺骸を鴨川に流すという 計画をしました。その企てを知ったお弟子達が、奥嵯峨の二尊院にご遺骸を 移して、お隠ししました。 しかし、すぐ知れわたりましたので、密かに当寺にお移ししました。そして、西光寺の開祖 来迎房圓空上人が、翌年の1月25日まで、ご遺骸をお護りしました。その後ご遺骸は、京都の西山の粟生野(後に光明寺)で、茶毘(火葬)に伏されました。 山門は、嘉禄の法難当時が偲ばれるように茅葺造りです。中央に、尋声という額があります。尋とは「たずねる」という意味があり、お念仏の声が偲ばれる寺院ということから命名しています。

法然上人立像
法然上人が、奈良東大寺 「三部経講説」の御帰りのお姿を現した像と言われています。 法然上人は、生涯 墨染の衣と灰色の袈裟で過ごされました。 この像は、専修念仏信仰の為にお召しになられた色衣と如法衣のお姿だと受け取っています。 (江戸時代作)
本尊 阿弥陀如来坐像
平安時代初期に造仏されました(9世紀後半頃) この像の台座背面に、この像が法然上人のお念持佛であったと記されてあります。又、「天福※ 来迎房圓空」と彫り示されています。(※天福とは、元号で1233年となります) 阿弥陀仏の膝上で組む定印(上品上生)では、初期の仏像に属し、通肩の大衣も、阿弥陀仏では貴重なご本尊です。 阿弥陀如来坐像は国の重要文化財指定がされています。
善導大師立像
中国(唐の時代)の僧で、法然上人の師僧です。 法然上人は、夢の中で善導大師にお会いされましたがそのお姿は下半身が金色で「弥陀の化身」であったと言われています。(江戸時代作)
子守地蔵尊
保育園や近隣の子ども達をお守り下さるお地蔵さまです。
法然上人御廟(御廟塔)
この石碑はもともと広隆寺山門前に設置されていたと伝えられています。(西1丁 西光寺円光大師遺蹟と刻まれています) 広隆寺山門前より移管後、御廟塔として設置しています。 円光大師とは、東山天皇から加謚された最初の大師号です。
西光寺の茅葺山門
西光寺の茅葺山門は、嘉禄の法難を偲べる建物保存の目的で、維持管理をしています。 最新の材料は、神奈川の西湖から調達し、葺き替えは20年周期です。
八臂弁財天
弁財天様は、江戸時代作で八つの腕に道具をお持ちになられている八臂弁財天様です。人々に弁才、無人の智恵、財宝、延命を与え、さらに悪夢・邪気・呪術・鬼神などの人を惑わうものを排除し、病苦や疾病、闘争なども遠ざけると伝えられています。
ご挨拶
仏教をもう一歩みなさまのところへ
京都 西の地 洛西 太秦にある西光寺の住職の木村と申します。
本日は、西光寺のホームページをご覧頂きまして、ありがとうございます。
西光寺は、京都にある知恩院の末寺です。嘉禄3年法然上人のご遺骸が鴨川へ流されようとした時に、迫害する勢力からご遺骸をお隠しした寺院です。当時 大谷(現知恩院)に埋葬されていたご遺骸を護る為に、奥嵯峨二尊院へお移しし、お隠ししました。
しかし、道中付添の弟子が多く、6日で気がつかれてしまったので、今度は数名のお弟子(絵伝では9名)だけで、当時 広隆寺の境内で庵を結んで専修念仏の教えに帰依されておられた来迎房円空上人の住房へ移し、円空上人が責任を以ってお護りしました。
その縁により嘉禄の法難の後に浄土宗の寺院となり、8ケ月間お護り通した来迎房円空上人をご供養し、今日に至っています。※京都府寺院明細帳によれば、文化9年(1812年)7月に知恩院の命によって、再建されたと記録が残っています。前年の文化8年は、法然上人の600年大遠忌に当たる年でした。
「文化九年七月 従知恩院宮蒙内命再建之」
知恩院所蔵の「勅修御伝」によれば、ご遺骸をお移しした所は広隆寺ということですが、京都市埋蔵文化財研究所地図広隆寺旧境内により、当時の広隆寺の境内は約6万坪 (現在は約1万坪 )あり、現
西光寺の敷地も南西角地付近に位置していたことが考察できます。
また西光寺が所蔵する、御廟の円光大師 (法然上人の大師号) の石碑は、旧広隆寺敷地内の霊蹟地という理由で広隆寺山門前に設置されていたものが、移転されたものです。
西光寺で約8ケ月間、追手から護られた後、今度は西光寺から西山粟生野にお移しして、その地で荼毘(火葬)に伏されました。その後 その荼毘地に建立されたのが、長岡京の西山浄土宗本山光明寺です。
今の世の中、物質的には豊かになったかもしれませんが、心はというと同じように豊かにはなっていないのではないでしょうか。今さえ良かったら良い、自分さえ良かったらそれで良い、そのような考えから大切なものを見失っている世の中ではないでしょうか。
まだまだ、皆様に何かをお伝えできるほどの身ではありませんが、法然上人の墨染のみ心を忘れることなく、今目の前におられる皆様に、しっかりと目を向け、「仏教を もう一歩 みなさまのところへ」を僧侶の使命として、出来る限り努力して行きたいと考えています。
どうぞ、よろしくお願いします。

永代供養墓希望の方へ
永代供養墓 合祀納骨墓 近いところで永代供養
後継者がおられないご夫婦、生涯お一人で過ごされた方といったそんなみなさまを末代までご供養させていただきます。(宗派不問)
遠方にお墓があり、お参りに行きづらくなられた皆様の改葬(お墓の引越し)の相談も受け付けています。
当寺は清掃を心がけて、お花(樒)を添えています。いつお墓参りに起こしいただいても、気持ちよくお参りしていただけるように墓地の様子を気にかけています。
お墓に入られる方、お参りにいただける方にとってこの地が永代に渡り静かで心休まる場所であるよう願っています。
生前予約も可能です。
納骨料・回向料・管理料・使用料 石塔撥遣・開眼料・本堂安置新位牌代・墓プレート
35万円※別途にお願いする料金(希望の方はお申込み下さい)
納骨手伝い 業者 1.5万円
大塔婆 1枚 3,000円
水塔婆 1枚 300円
諸事情があり、葬儀なし等でお骨がお手元にある皆様 相談下さい。
当寺の本堂で、お骨葬式 (戒名授与) と永代供養墓納骨を行えます。
■御電話でのお問い合わせ 075-861-0985(担当:木村)
■メールからのお問い合わせ お問い合わせ

嘉禄の法難
法然上人の生涯

奥嵯峨二尊院から、広隆寺来迎房円空の住房(後に西光寺)に、法然上人のご遺骸をご移葬した場面です。知恩院所蔵 国宝 『法然上人行状絵図』 の第42巻第5段より、知恩院の許可を頂き掲載しています。

大谷(現知恩院)から、嵯峨二尊院へご移葬している場面
第42巻第4段より

安らかにお眠りいただくために
現在、お墓のある菩提寺が無い皆様、お墓を作れる寺院をお探しの方、当寺、西光寺へお気軽にご相談下さい。
西光寺は、宗祖法然上人のご遺骸をお護り埋葬した由緒ある霊蹟地で、お寺の墓地に保育園(うずまさ保育園)の園庭が隣接し、墓地にも絶えず子ども達の明るく元気な声が届いています。
そして何よりも、西光寺は檀信徒皆様に寄り添えることが出来る寺作りに取り組みたいと思っています。
西光寺の墓地、そしてお檀家を希望される方は、ご相談下さい。
また、ご自宅へお伺いするお命日の月参りや、お盆期間中のお参りを希望されたい方は、当寺にご相談下さい。(浄土宗のお経でお参りします)
あわせて、ご一緒に埋葬させて頂く「合祀墓(永代供養墓 合祀納骨墓)」もございますので、あわせてご案内申し上げます。
お気軽にお問い合わせください。
お墓のお引っ越しなどのご相談も受け付けております。お問い合わせください。
※お檀家の皆様へ
檀家墓は、ご先祖様が大切に守られてきたお墓です。出来る限り、継承して頂きますようお願致します。
なお、西光寺では、本家以外の方でもお墓を継承して頂けます。ご兄弟・ご親族等で大切にお守り頂ける方がおられましたら、まず当寺にご相談下さい。

町内の地蔵盆 数珠廻しのお勧め
町内の地蔵盆
地蔵とは、サンスクリット語のクシティガルバの意訳で、クシティは「大地」、ガルバとは「胎蔵」のことであり、合わせて「地蔵」と訳されました。
お地蔵さんの正式名は、地蔵菩薩です。
地蔵菩薩はお釈迦様が入滅してから未来仏の弥勒菩薩がこの世に現れるまで、人間界のみにあらず地獄・飢餓・修羅・畜生・天といった六道すべてにおもむき、人々を救済されています。
この機会に、子ども達を囲んで地域のつながりを深められてはどうでしょうか。
数珠まわし用数珠のお貸し出し
皆様の町内地蔵盆では「数珠まわし」 をされていますか?
地蔵盆では数珠回しを行うことをおすすめしております。
当寺は寺の数珠をお貸ししています。お気兼ねなくお問い合わせください。
数珠回し用数珠の予約
電話:075−861-0985 担当木村までお問い合わせください
「数珠まわし用数珠」・「法話」を子ども達へ
数珠のお貸出は当寺住職がお持ちします。
その際、当寺では「法話」を実施させていただいております。
法話は「お地蔵さまと地域ご縁のおかげ」をお話させていただいております。
お貸し出しの流れ
お申込みは、お越し頂だき直接お申し込みいただくか、電話でお願いします。
その際、町名・代表者名・連絡先をお聞きいたしますのでよろしくお願いします。
※他のお貸出先との兼ね合い上、ご希望の時間の他でも調整させて頂くことがございますのでご了承ください。
※時間の都合上、遠方の町の方は、お断りさせて頂く場合があります。
※現在、他の寺院様にお参りに来て頂かれている町も、原則お断りしています。
ご連絡・お申込先
京都太秦:西光寺 住職:木村 信哉 電話:075-861-0985

アクセス
〒616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町30
075-861-0985
京福電鉄 太秦広隆寺駅より徒歩5分
JR 太秦駅より徒歩10分
京都市バス11番 太秦開町バス停より徒歩3分
京都バス73番他 太秦開町バス停より徒歩3分